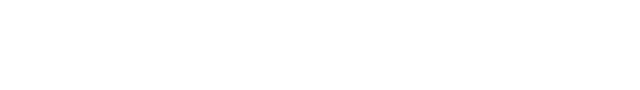【第1回】MRIの原理についてわかりやすく解説
皆さんはMRI検査を受けたことがありますか?
受けたことがある方でも、「MRIってどうやって撮影しているの?」「あの大きな音は何?」など、仕組みを詳しく知っている方は少ないかもしれません。
このシリーズでは、MRI検査に関する疑問を一つひとつ丁寧に解説し、検査への不安を少しでも軽減していただけることを目指しています。
第一回目は、「MRIの原理」について分かりやすくご紹介します。
① MRIでは「水」がキーマン!
MRIの仕組みを理解する前に、まずは「写真を撮る」という行為の原理について考えてみましょう。
スマートフォンのカメラは、物体に当たって反射した光をレンズで集め、イメージセンサーにより電気信号へ変換して画像化します。
医療現場でよく使われるレントゲン検査も、同様に「写真を撮る」という考え方が近いです。
レントゲンは放射線を使い、体を通り抜ける線量の違いによって濃淡の画像を作成します。CT検査もレントゲンと同様に放射線を使用しますが、断面を輪切りで撮るようなイメージです。
それに対してMRIは放射線を使いません。
では何を使うのでしょうか?答えは「水」、つまり水分です。人体の約60~70%は水で構成されており、水はH2O、つまり水素を含んでいます。
この水素の「原子核」、すなわちプロトンがMRIの画像作成において非常に重要な役割を果たします。
② MRI装置の中で人体はどうなっているの?
では、MRI装置の中に体が入ると、プロトンたちはどのような反応を示すのでしょうか?以下の流れで画像が作られていきます。
- 通常、プロトン(原子核)はランダムな方向を向いています。
- MRI装置内に入ると、強い磁場の影響で同じ方向を向きます。
- そこへ電波(RFパルス)を加えると、プロトンが別の方向を向きます。

- 電波照射が終了すると、プロトンは元の向きに戻ろうとします。
- その戻るときに、非常に弱い電波を出します。
この電波を「受信コイル」がキャッチし、電気信号に変換してコンピュータで画像化します。
戻る時間の違いは、組織の種類によって異なるため、これが画像のコントラスト(明暗)になります。
③ MRIに欠かせない「受信コイル」とは?
検査中、頭にかぶせるようなカバーを使うことがあります。
これが「受信コイル」です。
簡単に言えば、プロトンが発する微弱な電波をキャッチする「アンテナ」のようなものです。
ラジオが空中の電波を受信して音にするように、受信コイルは人体から発された信号を受け取り、画像データとして処理されます。
目的部位ごとに最適な形の受信コイルが用意されており、頭部用・腹部用・脊椎用などがあります。
④ MRI検査の音の原因とは?
MRI検査と音は切っても切り離せない関係にあり、撮影中にはどうしても大きな音が発生してしまいます。
結論から言うとこの音は傾斜磁場コイルが原因です。
MRIでは撮像の際に、装置の中にある傾斜磁場コイルに電流を流したり切ったりします。
すると傾斜磁場コイルが振動し、その結果大きな音が生じます。
そもそもこの傾斜磁場コイルというものは何のためにあるの?
プロトンから発生した電波が体のどこから出た信号なのかを把握するために、傾斜磁場コイルを使ってトンネル内の磁場に強弱(傾斜磁場)をつけます。
すると、弱い磁場の所から発生した電波と、強い磁場の所から発生した電波に区別することができます。
これによって位置情報を把握することで、目的の範囲を撮影することができます。
この傾斜磁場という特殊な環境を作り出すためには、傾斜磁場コイルに電流を流したり切ったりしなければなりません。
傾斜磁場は撮影が行われている限り必要です。そのため、コイルが振動し検査中に大きな音が鳴るのです。
⑤ まとめ
今回はMRI装置の基本原理についてご紹介しました。MRIでは、体の中にある「水分=プロトン」の動きを観察することで画像を作成しています。
頭にかぶせるカバー、検査中の音、装置の中でじっとしている理由、これら一つ一つにちゃんと意味があるのです。仕組みを知っていただくことで、不安や疑問が少しでも和らげば幸いです。
著:放射線技師Y
-
診療時間
月 火 水 木 金 土 日 10:00~13:30
受付は13:15まで● ● ● / ● ○ / 15:00〜19:00
受付は18:45まで● ● ● / ● / / 休診日:木・日・祝・第3水曜午後(院内研修のため)
○9:00~13:00 受付は12:45まで
-
交通案内
東京都練馬区練馬1-18-8 犬丸ビル2階