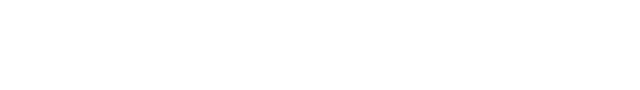しびれ
しびれとは
「しびれ」という症状は、人によって感じ方が異なります。一般的には、正座をした後に感じる「ジンジンする」「ビリビリする」「チクチクする」といった感覚を指します。
医学的には、「しびれ」は感覚異常の一つで、神経系や循環器系の障害により、運動神経や知覚神経が侵された状態(運動麻痺、知覚麻痺)と定義されています。
「しびれ」の語源ははっきりしていませんが、室町時代には「しびり」と言われていたようで、狂言の演目に「しびり」というのがあり「正座後のしびれ」によって動けないことを面白く扱っています。
これまで外来の中で、患者さんが表現する「しびれ」には、以下のようなさまざまな種類があります。
① 異常感覚(通常とは異なる皮膚の感覚)
- チクチク
- ヒリヒリ
- ビリビリ
- ジンジンする
- ムズムズ
- チリチリ
- うずく
- 圧迫されるような
- 皮一枚隔てられている
- 濡れている感じで不快
- 剥がれるような
② 運動異常(動かしづらさ・力の入りにくさ)
- 脱力感
- しびれて動かしにくい
- 鈍くて力が入れにくい
- 攣るような
③ 痛みを伴うしびれ
- 針で刺されるような
- 焼け付くような
- 痛いような
④ その他の違和感
- 火照り
- 冷たい感じ
- だるさ
- 重苦しい
- 違和感
- 麻酔をかけられたような
- 感じない
すぐに受診すべきしびれとは
日常生活の中でしびれは比較的よく遭遇する症状の一つですが、同時に心配な症状でもあります。
原因はさまざまですが中には脳梗塞や脳出血のように後遺症を残したり、命に関わる場合もあります。特に、突然のしびれ、片側だけのしびれ、動かしにくさがある場合は、脳神経外科の受診が推奨されます。
以下の特徴がある場合には脳神経外科・脳神経内科の受診を検討しましょう。
- 突然始まる(朝起きたらしびれている)
- 片側だけのしびれ
- 持続する(しびれが改善しない)
- しびれに加えて、動かしづらさや言葉の出づらさがある
- しびれとともに頭痛・嘔気・発熱がある
しびれがある場合、何科を受診すべきか?
「しびれ」には多くの原因があるため、どの診療科を受診すればよいか迷うこともあるでしょう。しびれを診断・治療する診療科には以下のようなものがあります。
- 脳神経外科
- 脳神経内科
- 整形外科
- 内科(膠原病・リウマチ内科、糖尿病・内分泌内科)
- 血管外科
- 精神科・心療内科
整形外科では、首や腰の異常によるしびれや末梢神経障害を診断・治療します。脳神経外科でもこれらの疾患を扱うため、どちらを受診しても大丈夫です。
ミネラルバランスやビタミン不足やホルモンバランスの異常、膠原病が関与するしびれは、膠原病・リウマチ内科、糖尿病・内分泌内科で診療されます。
血管の詰まりが原因で起こるしびれは血管外科が中心となって診断・治療が行われ、上記の病気のいずれも認めない場合には精神科や心療内科で心因性のしびれについて治療していくことになります。
しびれの原因
しびれの原因はさまざまで、次のようなものが挙げられます。
最も多いのが長時間の神経圧迫、ついでパニック発作(過換気)、脱水、循環不全、そして神経系疾患と続きます。
このようにしびれの自覚は脳でなされるのですが、原因は神経系にあるとは限りません。
また神経系の中でも末梢神経から大脳中枢に至る感覚神経系に異常がある場合と、それ以外の運動系、自律神経系にある場合、原因不明のもの、心因性のものがあります。以下にしびれの原因となる病態・疾患をまとめてみました。
【神経系以外の場合】
- 脱水
- 血行障害(閉塞性動脈硬化症など)
- 局所の組織障害(皮膚炎など)
- 代謝性疾患(低血糖、電解質異常など)
- 内分泌疾患(甲状腺機能低下症など)
- 血液疾患(貧血、真性多血症など)
- 更年期障害
- 薬物副作用の一部
- 過換気症候群
【感覚神経系にある場合】
末梢神経障害
- 絞扼性ニューロパチー
・手根管症候群
・外側大腿皮神経障害
・足根管症候群 - 糖尿病性ニューロパチー
- 遺伝性ニューロパチー
- 帯状疱疹
- アミロイドニューロパチー
- 小径繊維ニューロパチー
- 変形性脊椎症性神経根症
- 腕神経叢障害
- 転移性腫瘍・傍腫瘍性症候群
- ヒ素中毒
- 薬剤副作用の一部
脊髄病変
- 多発性硬化症
- 視神経脊髄炎
- 脊髄炎
- 脊髄空洞症
- 頚椎症性脊髄症
脳幹病変
- 延髄外側症候群
- 三叉神経入口部病変
- 脳腫瘍
視床病変
- 視床梗塞
- 視床出血
- 脳腫瘍
大脳病変
- 脳梗塞
- 脳出血
- てんかん
- 脳挫傷
- 脳腫瘍
【感覚神経以外の神経系にある場合】
筋・筋膜疾患
- 多発筋炎、好酸球性筋膜炎など
運動ニューロン疾患
- 筋萎縮性側索硬化症、Guillain-Barre症候群など
自律神経障害
錐体外路疾患
- パーキンソン病など
【その他・原因不明】
- Restless legs症候群
- 薬物副作用の一部
- 心因性
しびれの診断
原因が多岐に渡ることから、診断に至る過程も複雑になることがあります。しびれの診断を進めるためには、丁寧な問診・身体診察・各種検査が重要です。
1. 丁寧な問診
- しびれの範囲:指先だけか、腕や足の上の方まで広がっているか、片側か両側か
- しびれの種類患者さまが「しびれ」と表現するものが実際どのような感覚なのかオノマトペを用いた表現により探っていく。
(例)「ビリビリする」「チクチクする」
- 発症の仕方:突然か、徐々にか、増悪改善傾向
- しびれの持続性:ずっと続いているか、一時的か
- 悪化・軽減する要因:夜や朝に悪化するか、振ると改善するか
- 随伴症状:頭痛、吐き気、めまい、発熱、言葉の出にくさなどが伴っていないか
- 既往歴や生活習慣:薬や生活習慣が原因になっていないか
2. 身体診察
身体診察では実際に患者さまのしびれる範囲を目で見て、触って確認します。
皮疹がないか、皮膚の色の変化はないか、あるいは触った時にしびれが変化するかを確認します。
その後、腱反射や神経学的診察により脳や脊髄、末梢神経の働きを調べていきます。この際、感覚神経だけでなく筋力低下がないかも見ていきます。
診断を進めるために誘発テストがありPhalen徴候、Tinel徴候、carpal compression testやJackson徴候、Spurling徴候、Lasegue徴候、Kemp徴候、Femoral nerve stretch sign、Adson試験、Wright試験、Roosの3分間挙上負荷試験などといったさまざまな誘発試験があり、疑わしい疾患を念頭に置きながら行なっていきます。
3. 検査
画像検査
しびれの原因が脳や脊髄にあると考えられる場合にはCTやレントゲン、MRIを用いて画像検査を行います。
特にMRIは脳梗塞、出血、腫瘍を診断するためにとても役立ちます。
ただし、MRIでは骨の情報を知ることが苦手なことが多いため、骨の異常を調べるためにCTやレントゲンを用います(最近はMRIでも骨の情報を得られるようになってきている例:bone like image)。
血液検査
糖尿病や低血糖、貧血やビタミン不足、甲状腺機能の問題などを調べるために血液検査を行う場合があります。
特に長期にわたるしびれなどでは血液検査でこれらの状態を見ておく必要があります。
また筋炎や血管炎などの自己免疫疾患などの可能性についても血液検査で調べていきます。
その他の検査
髄液検査や神経生検などといった検査があり診断に有用ですがクリニックレベルではこの検査を行うことは難しいことが多く、この段階では総合病院・大学病院などへご紹介致します。
まとめ
「しびれ」症状についてお話ししました。
生活の中でしびれは比較的よく遭遇する症状の一つですが、同時に心配になる症状でもあります。
突然始まる、持続する、痛みや動かしづらさが伴う、頭痛や発熱などが伴う場合にはぜひ受診されることをご検討ください。
そして適切に診断、治療が受けられるようにしてきましょう。
文責:井上剛(日本脳神経外科学会 日本脳神経外科学会専門医)
-
診療時間
月 火 水 木 金 土 日 10:00~13:30
受付は13:15まで● ● ● / ● ○ / 15:00〜19:00
受付は18:45まで● ● ● / ● / / 休診日:木・日・祝・第3水曜午後(院内研修のため)
○9:00~13:00 受付は12:45まで
-
交通案内
東京都練馬区練馬1-18-8 犬丸ビル2階