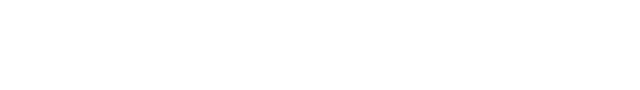くも膜下出血
〜脳卒中の中でも特に注意が必要〜
くも膜下出血とは
くも膜下出血は、脳の表面を覆う「くも膜」と「軟膜」の間にあるくも膜下腔に血液が流れ出る状態で、脳卒中の一種です。
脳卒中には、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などがありますが、くも膜下出血は脳卒中の中でも発症率は少ない一方、非常に重症になりやすいタイプの病気です。
日本では毎年およそ2万人がくも膜下出血を発症しており、脳卒中全体の約5%を占めます。
原因の約85%は、脳動脈瘤の破裂によるものです。40~60代の比較的若い世代にも多く見られますが、近年は高齢者での発症も増えています。
原因
1. 脳動脈瘤の破裂(最も多い)
くも膜下出血の原因の約80〜85%は、脳動脈瘤の破裂によるものです。
脳の動脈にできた「こぶ(動脈瘤)」が破裂し、くも膜下腔に血液が流出します。
突然の激しい頭痛(雷鳴頭痛)や意識障害で発症します。
2.脳動静脈奇形(AVM)やもやもや病などの血管奇形
脳の血管の先天的な異常が原因となることがあります。
動脈と静脈が直接つながっている部分(奇形部位)が破裂することがあります。
若年者のくも膜下出血では、この原因が疑われることが多いです。
3.外傷性くも膜下出血
交通事故や転倒などで頭部を強く打った際に発生します。
高齢者では軽微な外傷でも出血を起こすことがあるため注意が必要です。
4.血管炎や膠原病に伴う血管障害
全身性エリテマトーデス(SLE)や高安病などにより、脳血管が炎症を起こし破裂することがあります。
非典型的な症状で発症することもあります。
5. 原因不明(特発性)
画像検査で明らかな原因が見つからない場合もあります(「非動脈瘤性くも膜下出血」などと呼ばれます)。
血管の微細な損傷や静脈性の出血が原因とされることもあります。
危険因子
- 高血圧
- 喫煙
- 多量飲酒
- 家族にくも膜下出血の既往がある方(遺伝的素因)
症状
くも膜下出血の初期症状として最も多いのが「突然の激しい頭痛」です。
雷が落ちたような、バットで殴られたようなと表現されることがあり、頭痛を感じた直後に意識を失うこともあります。
その他の症状:
- 吐き気、嘔吐
- 意識がぼんやりする、または意識を失う
- 首を曲げた際に痛みが走る、曲げにくくなる(項部硬直)
- まぶしさを感じる、物が二重に見える、まぶたが下がるなどの眼の症状
- けいれん
- 発熱
特に今まで経験したことのない突然の激しい頭痛の場合は病院を受診するようにしましょう
診断
くも膜下出血が疑われた場合、迅速な画像検査が必要です。
- 頭部CT:出血の有無を即座に確認
- MRI(FLAIR、SWI):微細な出血の評価
- MRA・CTA:動脈瘤の形状・位置を確認
- 脳血管造影(DSA):詳細な血管情報が得られる
治療
治療の目的は「再出血を防ぐこと」と「合併症を抑えること」です。
出血の原因が動脈瘤である場合、再出血を防ぐ治療が最優先です。選択される治療法は次の通りです。
- 開頭クリッピング術:頭蓋骨を一部開き、動脈瘤の根元にクリップをかけて閉じる方法です。皮膚を切って頭蓋骨を一時的にはずし、脳を避けて顕微鏡を使って動脈瘤を挟み・潰すことで血液が入らないようにする手術。1〜2週間程度の入院
- 血管内コイル塞栓術:カテーテルを使って動脈瘤の中にコイルを詰め、血流を遮断する方法です。足や腕の血管から細いカテーテルを脳まで通し、プラチナ製のコイルと呼ばれる針金を動脈瘤内部に詰めることで動脈瘤内に血液が入らないようにする手術。数日から1週間程度の入院
- ステント留置術(Flow Diverter stent):網目の細かいステントを使って動脈瘤に血流が入らないようにする方法です。
どの治療方法にもメリット、デメリットがあります。動脈瘤の場所や形、患者様の年齢や体の状態を総合的に判断して選択されます。
合併症
くも膜下出血には以下の重大な合併症が発生することがあります。
- 再出血:発症後24時間以内が特に危険で、早急な処置が必要です。
- 脳血管攣縮(れんしゅく):発症から4~14日後に起きることが多く、脳の血流が悪くなるリスクがあります。
- 水頭症:脳脊髄液の流れが妨げられ、脳室が拡がってしまう状態です。
- 肺炎や心不全などの全身合併症もあります。
予後
日本脳卒中学会の統計では、くも膜下出血の死亡率は発症1か月で30〜40%、発症後1年以内では65%前後と非常高いとされています。
生存された方でも、以下のような後遺症が残る可能性があります。
- 記憶力や注意力の低下
- 手足の麻痺やしびれ
- 言葉がうまく出ない、理解できないなどの言語障害
社会復帰が可能な方は全体の約30%とされており、発症の重症度や治療までの時間によって大きく左右されます。
予防
くも膜下出血を防ぐためには、動脈瘤の破裂を起こさないようにすることが大切です。
【日常生活でできる予防】
- 高血圧の治療とコントロール
- 禁煙
- 飲酒量の節度を守る
- バランスのとれた食生活
- 適度な運動
- ストレスを溜めない
- 十分な睡眠
【検査による予防】
- MRIやMRAによる未破裂脳動脈瘤の早期発見
- ご家族にくも膜下出血の既往がある方は、特に定期的な検査をおすすめします
まとめ
くも膜下出血は、命に関わる病気ですが、早期の発見・治療により命が救われるケースも増えています。
頭痛がいつもと違う、急に意識が遠のいたといった症状を感じた場合には、迷わず病院を受診しましょう。
また、日頃から健康管理を意識し、定期的な脳の検査(脳ドック)を受けることが予防につながります。
-
診療時間
月 火 水 木 金 土 日 10:00~13:30
受付は13:15まで● ● ● / ● ○ / 15:00〜19:00
受付は18:45まで● ● ● / ● / / 休診日:木・日・祝・第3水曜午後(院内研修のため)
○9:00~13:00 受付は12:45まで -
交通案内
東京都練馬区練馬1-18-8 犬丸ビル2階